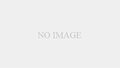プロレス的随筆徒然草(5) プロレスの技とリアリティ
試合の写真を撮ると
私はプロレスブログで観戦記を書いており、そのために約15年くらい前から、試合の写真を撮影するようになりました。
しかし、いかんせんカメラにお金をかけられないため、安いデジカメやスマホのカメラだと、撮影した写真の殆どがブレてしまいます。
これは、私の腕の問題、機材の問題もありますが、試合中選手が常に動いているのも原因のひとつかもしれないと思うようになりました。
感覚的に麻痺
要するにどこかでレスラーの動きが止まる場面があれば、そこに引き摺り込まれる可能性がありますけど、常時動きっぱなしだと、試合の山場もわからないし、繰り出される数々の技がどんなに凄くても、感覚的に麻痺してしまうのではないでしょうか。
ネットのアーカイブなどで残された昔の試合映像と比較すれば、昔の試合は殆ど選手同士が動かない展開が多く、現代では繋ぎ技にしかならないものでも、必殺技と実況されています。
大技を使わないプロレス
私が生まれる前の試合についてはわかりかねますが、プロレス生観戦をはじめた頃は、まだ技の数も少なくて、選手が常に動き回る試合は少なかったと記憶しています。
では、プロレスとは現代でいう大技を使わないと試合が成り立たないのか、というとそんな事はありません。
超人的試合=プロレス
しかし、基本技のみで組み立てられた試合がつまらないか、と言われたらそんな事はないはずです。
とはいえ、最初から大技がバシバシ飛び出す超人的試合が、プロレスだと信じてみている層にはもしかしたら刺さらない可能性はあります。
プロレスである理由
そもそも超人的な身体能力は誰のために、何のために披露されるものなのでしょうか?
それがプロレスでなければならない理由は何なのでしょうか?ここを突き詰めて考えていくと、どの技にもそれを繰り出す必然性があり、お客さんに納得してもらえる必要があるはずです。
一つ一つの凄さ
プロレスに強さを求めるくらいなら、総合格闘技を見ればいいというのであれば、驚異的な身体能力も、それこそ体操競技で見ればいいという理屈になってしまいます。
どんなすごい能力や技でも、それが立て続けに飛び出してきたら、一つ一つの凄さがよくわからなくなるように私には思えてなりません。
それは、プロレスラーが考えないといけないプロレスのリアリティなのではないでしょうか?
技を出す必然性
プロレスで表現できるリアルは、バックボーンだけでなく、闘う選手の感情表現や、試合運び、理にかなった技の数々…と、枚挙にいとまがありません。
技を繰り出す「必然性」とは、その技が試合の流れやキャラクターの設定、ストーリーラインに合致していることも意味するのです。
自然で説得力がある
観客が納得するというのは、技が自然で説得力があり、感情を揺さぶるような展開であることも求められます。
例えば、悪役が反則技を使う場合、それがその選手のキャラクターに合っていて、物語の中で高まる緊張感を生み出すなら、観客はその技に対して怒りや興奮を感じる可能性が高まります。
物語を伝え感情を動かす
また、ベビーフェイスが大逆転のフィニッシュムーブを決める時、それが試合のクライマックスとして盛り上がりを見せる事で、観客は喜びや感動を共有できます。
プロレスの技は、ただ単に相手を倒すためのものではなく、観客に物語を伝え、感情を動かすための手段にもなっています。
観客との心理的やりとり
そのため、技には必然性が求められ、観客が納得し、感情移入できるような展開が大切になってきます。
プロレスの魅力の一つには、観客との心理的なやり取りがあると言えるでしょう。
意図と物語を伝える
どのような技も、その背後にある意図とストーリーが観客に伝わることが重要になってきます。
今のプロレスは身体能力の化け物みたいな選手が、人間業とは思えない空中戦などを披露するのが主流にはなっています。
リアルを損ねる
しかし、あまりに行きすぎてしまうと、どちらが技を仕掛けて、どちらがやられているのか、私も分からなくなる時があります。
プロレスのリアルを損ねているものに、私はチョップのラリーもあげておきたいと思います。
プロレスのチョップというのは意外と難しくて、鍛え抜かれたレスラーの胸板に素人がふざけてやろうもんなら、手を痛めてしまいます。
ダメージが伝わりやすい
基本的な技術だけに舐めてかかれない技の典型例でしょう。
プロレスのチョップは視覚的にもダメージが観客に伝わりやすいという利点があります。
プロレスの醍醐味
実際、技術があるレスラーのチョップは、鍛え抜かれたレスラーの胸板を真っ赤にはらし、内出血を起こしたり、裂けて血が出る場合もあります。
あの乾いた音が会場に響き、汗が飛び散る中、傷だらけの選手たちが胸を突き出してチョップを受け合う姿はある意味プロレスの醍醐味でもあります。
使い方を誤ると
チョップは基本技ではあるし、胸が裂けるのはリアルですから、一見すると理にかなっているように思えます。
しかし、これも使い方を誤るとプロレスのリアルを崩してしまう行為につながります。
我慢比べ?
それまで普通にプロレスの試合が進んでいた中で、急に始まるラリー、そして我慢比べ。会場は盛り上がりますが、前の展開との整合性がないまま、急に繰り出されるチョップ合戦には、私はどうしても違和感を感じてしまうのです。
2010年に上京した際、グレートカブキさんのお店に伺った際、カブキさんがこのチョップ合戦に苦言を呈してらした事は今でもはっきり覚えています。
カブキさんの金言
「チョップ合戦というのは、ある意味お客さんに乗せられてやっているだけ。本来プロレスラーの仕事はお客さんの想像を超えていくことにある」というカブキさんの言葉は今でも私にとっては金言になっています。

写真を撮る側の立場でいうと、チョップ合戦は、空中戦と異なり選手がぶれずに撮影できる利点があるのですが、観戦記にはほとんど使えません。
なぜなら全部同じような絵になってしまうからです。
フレアームーブ
一時期WWEは、リック・フレアー選手に敬意を表して、実の娘であるシャーロット選手以外のスーパースターズに、試合でチョップを禁じたという噂が流れていた事がありました。
あちらでは、フレアームーブの代表格である水平チョップが出ると、観客がフレアー選手の叫び声を真似して「Wooooo!!」というチャントが発生しますから、あながち間違いではなかったのでしょう。
エンタメに必要なリアル
日本もいっそ水平チョップを一度禁じ手にして、試合をしてみたらいいのに、と何回思ったかわかりません。
プロレスというのはエンターテインメントなんだから、リアルなんかなくていいと考えている人がもしいるのであれば、それは間違いだと言わざるを得ません。
リアルの重要性
プロレスを含むすべてのエンタメにリアルは必要ないのか?といわれたらそんなことはないでしょう。
エンターテインメントにおいてリアルの重要性は、人々の感情や興味を引きつけ、深い印象を残すためにも不可欠です。
説得力の放棄
そもそもスポーツエンターテインメントを標榜するWWEでは、先に述べた禁則事項の他に、レフェリーの前で行う反則には厳格なジャッジが下されます。
プロレスがエンターテインメントだからと言ってリアルを疎かにすれば、それは説得力を自ら放棄するようなものです。
リアルを犠牲にしない
プロレスは、そのエンターテインメント性とリアルさのバランスが非常に重要な要素です。
エンターテインメントとしてのプロレスは、観客を楽しませる前提はありますが、それによってリアルな競技性を犠牲にしてはなりません。
過度な演出は
プロレスの魅力は、予測不可能な展開と選手たちの技術的な実力にあるからです。
プロレスにおける演出が過度になりすぎると、試合のリアリティを損ない、観客を失望させる可能性があります。
真剣な努力の結果
プロレスラーたちの技術や創造性は、単なる「エンタメ」ではなく、観客を楽しませるための真剣な努力の結果としてとらえるべきでしょう。
試合でのライブ感や、プロレスラーたちの即興力も見どころの一つです。
それはただのアスリートではなく、エンターテイナーとしての側面も持っているプロレスラーにしかできない芸当です。

リアルな競技性
そのため、プロレスラーには、多岐にわたるスキルが求められるのです。
特に日本のプロレスは、リアルな競技性を保つことが重要ではないかと私は思います。
どんなに時代が変わっても
観客が感動し、興奮するためには、リアルさは必要不可欠です。
プロレスのエンターテインメント性を高めるためにも、リアルな競技性を疎かにすることなく、絶妙なバランスをとることが大切なのです。
プロレスにおけるリアルと説得力は、どんなに時代が変わっても、突き出されてくる課題だと言ってもいいでしょう。