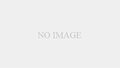松江だんだんプロレス主催試合「BATTLE DIMENSION 5」Inスサノオカフェ
(2016年3月6日(日)会場/スサノオカフェ特設リング)
イントロダクション
松江だんだんプロレスは総合格闘技団体「YAMATO」を母体として派生した社会人プロレス団体。2010年5月から松江市を拠点にして活動を開始した。勝ち負けではなく、観客を感動させ、そして困難に立ち向かう強い心や明日に向かって生きる勇気を与え続けていくことを目指している。また、プロレスを通じた地域の活性化をすすんで行っている。(ウィキペディアより)
最初は予定になかっただんだんプロレスだが、二転三転した末、行くことにした。観戦記では割と何回も書いているが、隣県の県庁所在地(松江)にいくのに、交通費が5000円以上かかり、しかも片道約半日かかる。もちろん高速道路も完全に伸びてなければ、新幹線も航空便もない。そのうえ三月になってなお山間部には雪が積もる。
基本移動は在来線か車かでしかない。鉄道ならば山口、広島、岡山経由で乗り換えになる。だから滅多なことでは行く機会もない。祖母の墓参りも亡くなって37年たってはじめていったくらいだし。
ただ、松江は母の故郷でもあり、小さい頃はよく泊まりに連れていかされていたので、土地勘だけはある。まあ、あちらの親戚とはあまり関わり合いになりたくないという個人的な事情もあるので、松江行きは誰にも告げず、参戦するがむしゃらプロレスメンバーにお世話になって現地に向かうことにした。
オープニング
でついてみてびっくり。母の実家がある街と会場のスサノオカフェがとんでもなく近い距離にあったのだ。本当に驚いた。まあ小学生の行動距離からは遠いのだが、車で行けば5分と離れていない。しかも到着するまでの間に親戚のうちの近くや、実家の近くを通ってしまったので内心かなり焦った。
で、だんだんプロレス初観戦を決めた動機はやはり昨年11月に流出したGWAタッグベルトの奪還戦が組まれていたからだ。しかもメインイベント。ただだれがチャレンジしても、王者チームがやすやすとベルトを手放すイメージがわかない。
それだけに、挑戦者チームの七海・ゲレーロ組がどう予想を覆すのか?また他のがむしゃら勢もアウェイでどう活躍するのか?興味は尽きないのである。
オープニングアクトを務めたご当地アイドルがマイクで「神聖な場に立たせていただいて」と感謝の言葉を述べていたが、口だけでなく、ちゃんと土足を脱いでリングに上がっていたのは感心した。
第一試合
×宇津宮卓也 vs ○嫁島健太郎
宇都宮は上半身が鍛え抜かれた感じがして、上背もある。黒のショートタイツが若々しさをアピールしていていい感じ。しかし守りに回ると打たれ弱くみえるのは、マイナス。あとグラウンドはもう少しねちっこくいってもいい。あっさり手を放していたのは気になった。ただ長身から繰り出されるドロップキックは見栄えがしてよかったと思う。
一方の嫁島はいわゆるUWF系の格闘プロレスタイプの選手。回し蹴りには威力を感じたが、ストンピングは迫力不足な感じがした。バチバチいくんなら、プロレス流のモーションに迫力が欲しい。
決まり手になったアームロックも、格闘技なら決めてさえいれば、お客から見えなくても問題ないが、プロレスでは決めたうえでそれを客席側に見せることが要求される。
嫁島のアームロックは自分が相手に覆い被さった状態で相手の身体の下で決めていたため、体重が乗っかってキツイ決まり方だったとは思うが、あれでは伝わるものも伝わらない。総合系選手の悪いクセといえばそれまでだが、改善すべきポイントはたくさんある。
いずれにせよ、宇都宮は原石には違いないが荒削りな感じがした。第一試合にあぶれるくらい若手がいると団体の未来も明るいのだけど。
第二試合
△グレートカグラ(TeamJoker) & 豪右衛門 vs △伊勢宮ジロー & 陽樹(両者リングアウト)
この試合は内容云々よりレフェリーに難がありすぎた。乱闘の際に試合権利がある選手サイドにのみ向けてカウントを数えないと、お客さんには不親切だし、リング内で決着つける気がない選手には没収試合に処すくらいの厳しさも欲しかった。またこういうカウントこそリングアナなりMCなりを使わないと不親切だろう。
でないと、悪役になめられているレフェリーの権威をお客さんも信用しなくなる。そうなるとカグラが云々いうよりやはり毅然としないレフェリーがこの試合をグダグダにしたと思う。
試合自体はカグラが陽樹を付け狙う感じもみてとれたが、これで抗争が続くのか?といえば微妙なところである。
あと、この試合だけではないが、だんだんプロレスの上位陣と若手の間に実力の落差がありすぎるように思う。全体的な底上げも必要な気がする。こういう不透明な試合はあってもいいけど、間に口直しできる存在がいないと、今のままでは表現の仕方には難ありと言わざるをえない。
第三試合
○YASU vs ×スサノオキッド
底上げが必要なところでいうと、だんだんのジュニアがやはりそう。ミステリコヤマトが純ジュニアヘビー級かというとそうではないし、となるとジュニア戦線を1人で回しているのが、スサノオキッドということになる。
だが、スサノオキッドの私生活は何気に忙しい。本業ほったらかしで遠征にいける時間的な余裕がない以上、他団体から強豪を呼んで対戦していくしかない。そこへいくとYASUはまぎれもない他団体から来襲した強豪であり、難敵であることには違いない。
試合のクオリティも要所要所でYASUがヒールモードになるものの、基本ジュニアの熱い攻防であり、スサノオがGWAジュニア王者に拮抗する逸材であることを証明していた試合だったと思う。途中で繰り出したジャべの数々は彼が飛ぶだけの選手でないこともうかがわせた。さすがにジャンプ力がすぎてYASUの背中が天井の空調の羽根にぶつかった時はヒヤリとしたけど。
そのYASUも狭いリングを有効活用して上に飛べない分、様々な形で空中戦を織り交ぜてきた。こちらも高い対応力と適応性で柔軟に試合を進めていく。
まあ、この試合に手ごたえを感じたからこそ、試合後にYASUがマイクをもち「めちゃくちゃ楽しかったです!」とアピールしたのだろうし、それは本心からだったと思う。
本来なら「北九州にきてベルトに挑戦しに来い!」となるのがプロレスならではのセオリーだと思うのだが、それが言えないもどかしさみたいなものも言外に感じてしまった。それくらい手の合うもの同士だけにもっと数多く二人の試合をみてみたい。まあ、これは仕事あっての社会人プロレスならではの悲哀だな、とおもった。
第四試合
×鉄生 & 林祥弘 vs ○ダイナマイト☆カドワキ & ALLマイティ井上
山陰統一タッグ王者、ALLマイティ井上とダイナマイト☆カドワキが、ノンタイトルながらgWoの実力派である鉄生と林を迎え撃つタッグマッチは予想通り白熱した攻防。
驚いたのはラグビー経験者の井上に鉄生が真っ向からぶつかり勝負を挑み、しかも吹っ飛ばしているのは、見ていて頼もしかった。
北九州ではあまりこれといった印象がないALLマイティだが、さすがに山陰統一タッグ王者はだてではない。ローンバトルを強いられても、我慢できる打たれ強さと、メンタル面の強さも感じられた。
林や鉄生の「じじい」呼ばわりには井上もキレ気味になってはいたが、逆にあれはgWoにしてみればヤブヘビだったと思う。
そしてダイナマイト☆カドワキもサイドをしっかり固められる好素材。最初は様子見でみていたけど、井上をサポートし、時には前に出て、試合を組み立てていた。 ダイナマイトの名を冠した社会人レスラーはなんかどこも独特だなあと思ってしまった。
林・鉄生組にも幾度となくチャンスはあったが、攻め所でのタッグワークは山陰側が一枚上手だった。個々の実力では決して劣らない林・鉄生が敗北したのはまさに経験値の差であり、王者の意地が上回ったのだと思う。タッグマッチの奥深さを感じた試合だった。
メインイベント~GWA 無差別級タッグ選手権試合
[挑戦者]×七海健大 & トゥルエノ・ゲレーロ vs ○マツエデラックス & ミステリコヤマト[王者]
昨年11月にベルト流出以来満を持しての奪回戦。チーム凱から七海健大・トゥエルノ・ゲレーロ組が挑戦表明!チャレンジャーとしては申し分ないが、いかんせん、団体のエースと、山陰統一王者の現タッグ王者は強い。個々の実力も素晴らしいがチームとしても強いのだ。
だから及び腰になるのはわからないでもないのだが、それでもわざわざ敵地に赴いて奪還を目指すにしては七海健大が最初から引き気味になっていたのは気になった。それは行きの車中からすでにみられていたので、大丈夫かな?とおもっていたが、まさか嫌な予感が的中しようとは…
マツエデラックスは巨漢で動けて頭がキレる曲者だが、一つ光明を見出すとしたら、長時間のローンバトルでデラックスのスタミナを奪う手にでるしかない。がむしゃらサイドからしたら、長時間闘い抜いて辛抱しきれたら、勝ち目があるかもしれないと踏んだ可能性はある。
だが、その予想は甘すぎた!15分過ぎて一旦切れかけたとみえたマツエデラックスのスタミナ。しかし彼はまだ余力を温存していたのだ!正直我々も騙された。スタミナだけではない。七海健大と真正面からラリアットを打ち合ってもふらつきもしない下半身の強さに、巨漢ながらにして受け身もなかなかとくるとこれは難攻不落の要塞に等しい。
さらに驚くべきは20分過ぎに攻めに出たがむしゃら組を二人まとめてなぎ倒し、ジュニアのゲレーロではなく、七海健大をターゲットにフィニッシュを畳み掛けてこようとは!スタミナ切れにみえてからの底力まで隠していたなんて!
正直今回はマツエデラックスの独断場に近い形で結果的には七海健大が向こうの思惑どおりにピンフォールをとられてしまったのだ。
今振り返ると、カットプレーが多かったのは明らかにがむしゃらサイド。しかも急増タッグの悲しさゆえに、会話でコミュニケーションしていた。片や王者組はカットプレーも少なく、会話する場面もない。カットプレーが少ないと片方が試合している時に控えの選手は呼吸を整え、ダメージの回復ができる。しかも、今回の場合マツエデラックスをまたしても全面に立てて試合していたため、ミステリコヤマトの実力を開示することなく、決着をつけてしまった。従って現時点でもミステリコヤマトの実力はまだヴェールに包まれたままなのだ。
対策としては七海・ゲレーロ組に経験を積ませてタッグ屋としてのスキルをあげる、タッグトーナメントを開催してほかのタッグ向きな人材を育てる、などをするしかあるまい。
おさまりがつかないのか、フライングぎみにgWoが飛び出してきて、勝手に次期防衛戦を一方的に決めてしまった(しかも場所は北九州)が、まあ、あの悔しい気持ちはよくわかるし、同時にマツエデラックスとミステリコヤマトが魅力的なターゲットとして認識したともいえるだろう。だが、王者だからあえてアウェイで挑戦を受ける必要もないのに、受諾した王者組は相当自信があるのか?
後記
正直他団体とのタイトルマッチであろうとも公平な目線で見るのが通常なのだが、やはり予想を上回る王者組の盤石ぶりに挑戦者チームがまんまと一敗地にまみれる姿を目にすると、悔しさが先に立つ。
その証拠に普段なら勝者をたたえていくのを、あえてだんだんの誰にも挨拶せず会場をあとにしてしまった。ついでに会場近くの神社にお参りまでしてきた。そうでもしないとおさまりがつかなかったのだ。今思うと挨拶くらいはしておけばよかったかなと思ってるけど。
で、負け惜しみになることを承知で書くが、やはり進行面ではアラが目立つ大会だった。具体的にはMCによるテーマ曲の掛け間違え、選手名の誤読…割りと演出部門の初歩の初歩ができてない感じがした。だから進行面では、なんとなく間延びした感じがした。このあたりは課題として改善してほしいポイントである。
また、正面がカメラ側なのか、入り口側なのかもイマイチわからなかった。よかった点はタイトルマッチで通常なら一方向正面のみで行われる記念撮影を客入れした三方向にむいていた点でこれは見習うべき点としてあげておく。
ともあれ、怪我なく遠征を終えたことはよしとしたい。長旅に長の運転、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。